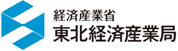東日本大震災から10年を迎えて
東北経済産業局長渡邉 政嘉

まず始めに、東日本大震災から10年の節目を迎えようとしている中、2月13日の福島県沖地震で被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申しあげます。
東日本大震災からの復旧・復興に大変な御努力をされてこられた方々は、一昨年の東日本台風においても甚大な被害を受け、現下の新型コロナウイルス感染拡大の影響、更に今回の地震と、度重なる自然災害等に見舞われ、事業継続への気力を失いかねない厳しい状況にあります。
今回の地震により、被災地の方々の復興に向けた希望が失われるようなことがあってはならず、一刻も早く被災者に寄り添った支援を行ってまいります。
2011年3月11日、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年が経過しました。
あの日、私は、茨城県つくば市に拠点を構える独立行政法人産業技術総合研究所の職員として勤務をしていました。研究所は通常のオフィスビルとは異なり、様々な研究設備や化学物質等を所有していたため、安全対策の観点から敷地建物内への入場は厳しく制限され、復旧までには多くの時間を有したのを記憶しています。
東北地域の産業復興はこの10年間で大きく前進し、地震・津波被災地域では復興の総仕上げの段階に入るとともに、原子力災害被災地域においても復興・再生が本格化しています。
この間、東北経済産業局では、東日本大震災からの復旧・復興に際して、各県、市町村をはじめ関係各位の御理解と御協力をいただきながら、ハード面での復旧・復興支援に加え、新商品の開発や販路開拓等といったソフト面での支援を行い、地域産業の活力の回復・向上に向けて取り組んでまいりました。
特に中小企業等の施設等の本格復旧に対する支援として、2011年から、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(通称グループ補助金)の交付を開始し、これまで663グループ、10,231件、5,098億円の交付を決定し、被災事業者の早期復旧と、事業再開を支援してまいりました。
さらに、三陸自動車道をはじめとするインフラ整備が進捗した津波被災市町村や避難指示が解除された原子力被災市町村等では、商業機能の回復、定住人口の確保や交流人口の拡大に向け、その中核的な施設として商業施設の整備を支援し、例えば、宮城県女川町では「シーパルピア女川」や「地元市場ハマテラス」の商店街施設を中心に行政施設や金融機関、温泉施設などが整備され、町民の日常生活を支えるだけではなく、来町者のニーズに対応する賑わいの拠点となっております。
また、雇用の維持・創出や地域の産業振興を促進するため、企業の新規立地に対する支援を行い、800件を越える製造業の生産拠点等の新増設が行われております。
グループ補助金を活用することで事業の再開を果たし、さらに新たなチャレンジを行うことで、震災前の売上げを越える事業者がある一方、沿岸部の水産加工業者などでは、販路の回復に時間がかかり、厳しい現実に直面している事業者も少なくありませんでした。
このため、当局では「三陸を世界トップの水産ブランドにする」とのスローガンのもと、2016年に三陸地域水産加工業等振興協議会を立ち上げ、三陸ブランドのプロモーション、新商品の開発、海外展開の促進、人材育成などを支援してまいりました。
この間、地域企業の連携による地域商社等が設立され、海外市場の新規開拓等への支援を行うことで、一定の成果も現れ始めており、引き続き三陸の水産ブランド化や競争力強化に向けた取組を推進してまいります。
原子力災害被災地域においては、2020年3月までに帰還困難区域を除き、全ての居住制限区域、避難指示解除準備区域が解除されたところです。
こうした中、原子力災害被災地域の産業復興に向けて、新規雇用の創出や産業復興を加速するため企業立地への支援を積極的に行っているほか、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクルなど6つの分野を重点分野と位置づけ、新たな産業の創出を目指し、国、福島県、市町村が連携して取り組む「福島イノベーション・コースト構想」が策定されました。特に「福島ロボットテストフィールド」が2020年に全面開所したところであり、今後、国内のロボットの一大開発実証拠点としての活用の促進が見込まれ、さらには、2050年カーボンニュートラルの達成に向け重要な実験施設となる「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」も稼働しており、これら産業の先進地域としての発展に期待しているところです。
東日本大震災における減災・防災上の教訓は、今後大規模災害が予測されている他地域においては貴重な情報となります。当局では、南海トラフ地震などが想定されている西日本を中心に各地に赴き、学識経験者や被害を受けた企業経営者等による講演会を開催し、防災・減災の知識や復興への取り組み状況をお伝えするとともに、被災現場の視察等を通じた交流人口・関係人口の拡大や、未だ根強く残る風評被害の払拭に繋げるための機会創出を行ってまいりました。
現在、被災地では、人口減少、高齢化の進展により様々な社会課題が顕在化する中で、地域の担い手不足という問題に直面しております。他方、震災を機に、復興支援やボランティア等多くの方々に来訪いただいたことで、東北各地が域外の専門家や若者等と繋がる機会が増大し、こうした関係人口が地域活性化の一翼を担う傾向が見られます。当局としても、プロボノ事業(注)等を通じ、引き続き関係人口を地域に取り込み、地域の新たな価値の共創が起こる「地域の可能性を最大化する持続可能なエコシステム」の実現を目指します。
- ビジネスパーソンが自分の専門知識やスキルを活かしておこなう社会貢献活動
今後は、復興の新ステージに向け、短期的には、沿岸被災地域の復興の完遂と、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえたニュー・ノーマルへの対応、中長期的には、カーボンニュートラルの達成や福島イノベーション・コースト構想などの産業戦略も取り込んだ自律的な経済再生を見据えております。
東日本大震災からの復興の過程で得た数々の知識や経験は、次世代を生き抜く力となり、このコロナ禍における逆境をもチャンスと捉え、乗り越えていけるものと信じております。
東北経済産業局といたしましても、この10年という節目にあたり、あの日失われたものの重さにあらためて思いを巡らせ、あの時誓った東北を復興させるという思いを新たに、職員一丸となって、関係者の皆様と共に復興に取り組んでまいりますので、御理解・御協力を何とぞよろしくお願いいたします。
令和3年3月11日
電話:022-221-4856
FAX:022-261-7390