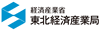【宮城県】雄勝硯(おがつすずり)

伊達藩が一般の採掘を許さなかった天然石「雄勝石」を使った硯の名品。近年は硯以外の新しい工芸品も生み出しています。
登録情報
雄勝硯 商標登録第5727126号
権利者
雄勝硯生産販売協同組合
商品の区分並びに指定商品
16類:宮城県石巻市雄勝町から産出する黒色の粘板岩を使用して作られる硯
出願日
2014年9月30日
登録日
2014年12月19日
連絡先
雄勝硯生産販売協同組合
住所:石巻市雄勝町下雄勝2丁目17
電話:0225-57-2632
商品の紹介
天然石を使って作られる硯
石巻市雄勝町で採れる「雄勝石」と呼ばれる天然石を使って作られる硯です。原料となる雄勝石は、別命「玄昌石」とも呼ばれ、地質学的には2から3億年前に属する黒色硬質粘板岩であり、 純黒色で圧縮・曲げに強く、吸水率が低いため、永い年月にも変質しない性質を持っています。その特性を生かして、古くから硯の原料として利用されています。また、近年は硯以外にも雄勝石を 使った新しい工芸品も世界的に評価されています。
独眼竜政宗にも認められた逸品
雄勝硯に関する古い記録によると、室町時代の応永3年(1396年)には硯石が産出されていたそうです。また、江戸時代の文献には、男鹿半島を鹿狩りに訪れた伊達政宗に硯が献上され、
賞賛を受けたとの記録が残っており、伊達家では硯師をお抱えとして、一般の採掘を許さなかったそうです。こうして、江戸時代後期には既に特産品となっていたようです。
明治期・大正期になると、近代化に合わせて多くの建物に雄勝産の石瓦材(天然スレート)が採用されるようになりました。昭和60年には、国の伝統的工芸品として指定を受けました。
東日本大震災を乗り越え、硯職人たちが手作業による硯づくりを受け継いでいます。
「雄勝硯」ブランド化の軌跡
雄勝硯はかつて、国産硯の9割のシェアを占めていました。特に昭和の後半までは、学童用硯を中心に需要を支えましたが、墨汁の普及から硯の需要が激減し、産業としては衰退してゆきました。
現在は高級硯に特化した生産となり、生産量は最盛期の1割程度となっています。また職人の高齢化も深刻で、正式な硯職人は60から80歳代の5人しかおらず、技術の継承が問題になっていました。
そのような状況の中、追い打ちをかけるように東日本大震災が発生し、雄勝町は甚大な被害を被ったのでした。
震災後、硯を地域ブランドとして、伝統産業を再生復興しようと、震災復興支援早期審査を利用して地域団体商標の出願を行い、平成26年に登録されました。これにより、雄勝石を利用した工芸品の
開発にも拍車がかかり、雄勝石の持つ「圧縮や曲げに強く、保温性と保冷性にも優れる」特徴に着目。生活に密着した雄勝石の魅力を引き出した調理用プレート、テーブルウェアやクラフト等が
開発されました。
さらに、イタリア・ミラノ国際博覧会への石皿の出展や、仙台市で行われた先進7か国財務相・中央銀行総裁会議で披露された酒器が好評を博したことは記録に新しいところです。
世界に一つだけの「my硯」を作ってみては?
書道・書画用品の専門店、伝統工芸品を取り扱う店舗やネット販売でも比較的簡単に見つけることができます。現地では雄勝硯生産販売協同組合への訪問をお勧めします。2020年5月に 雄勝伝統産業会館が新しく開館しました。雄勝石を使った体験・ワークショップを実施しており、世界で一つだけの自分用のmy硯をはじめ、手頃な費用でコースター制作が体験できます。 また、硯づくりの見学会やオリジナル製品の提案なども可能となっています。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」