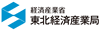【宮城県】仙台味噌・仙台みそ

伊達政宗によって自給生産された仙台味噌が始まり。そのおいしさと質の高さは、諸大名や庶民の間で評判になりました。
登録情報
仙台味噌 商標登録第5032789号
仙台みそ 商標登録第5032790号
権利者
宮城県味噌醤油工業協同組合
商品の区分並びに指定商品
30類:仙台藩に由来する製法により仙台を中心とした宮城県の地域内で生産されたみそ
出願日
2006年5月18日
登録日
2007年3月16日
連絡先
宮城県味噌醤油工業協同組合
住所:仙台市青葉区一番町二丁目11番1号
電話:022-221-7371
商品の紹介
400年以上の歴史
仙台味噌は江戸時代から400年以上の歴史がありますが、戦国時代から全国的に有名でした。伊達政宗が戦陣食として重宝した赤味噌を軍用味噌として仙台藩の自給生産で発展させた からです。米麹と大豆、塩を原料とした米味噌で、さえた赤色と良い艶、大豆のうまみが生きたすっきりとした味わいが特徴です。時代を超えて受け継がれる伝統的な製造法と宮城の気候 風土が醸す格別な味が魅力です。
日本初の味噌工場を作った伊達政宗
豊臣秀吉の「文禄の役」の際、朝鮮に出兵した他の大名の味噌が夏場に腐ってしまったのに対して、伊達政宗の持参した味噌は変質しなかったので「伊達家の味噌は質が良い」と諸大名の 間で、一躍脚光を浴びることになりました。その後、伊達政宗が仙台藩を開くと、軍用の味噌を自給しようと考え、城下に「御塩噌蔵(ごえんそぐら)」と呼ばれる味噌工場を建設し、城下の 老舗商人に製造と運営を任せました。これが今日の仙台味噌の始まりと言われています。また、江戸藩邸に常勤する藩士のために、江戸にも御塩噌蔵の制度を設け、原料は全て海路で仙台から 運び、賄いました。風味佳良なことを聞き、分与を乞うものも多く、二代忠宗の時代に一般に払い下げたことから、仙台味噌の名が広く知られるようになりました。
「仙台味噌」「仙台みそ」ブランド化の軌跡
仙台味噌の製造は藩によって保護され、商業発展とともに城下の味噌屋たちが同業組合を結成して、品質と価格の安定に努めました。味噌屋では「味噌屋仲間掟留帳」を定め、生産から販売、
雇用関係に至るまで厳しい掟を決めました。現代においても、その意志を受け継ぎ、伝統を守るべく基準を設け、仙台味噌の品質向上とブランドとしての統一化が図られています。地域団体商標は、
ブランド化のために出願、平成19年に登録を得ました。
それぞれの味噌蔵では、消費者に末永く愛される「仙台味噌」を目指し、オーガニック素材を使った有機味噌や県産の原料を使った宮城県認証食品(Eマーク)を取得している味噌、自社農場で
大豆と米を作り原料としている味噌などを造り、代々伝わる伝統の味と技術を守りながらも、より特徴のある製品開発が行われています。また伝統的に培われた「本場」の製法で、地域特有の
食材などを用いて「本物」の味をつくり続けるこだわりの証として、一部は地域食品ブランドの表示基準「本場の本物」にも認定されています。
また、最近では機能性をもたせた味噌を開発しました。骨粗しょう症の予防などに効果がある大豆に含有しているポリフェノールの一種である「イソフラボン」は、味噌の製造過程において腸内で
吸収しやすい「アグリコン型イソフラボン」という形に変わることが分かっています。これまでの仙台味噌はイソフラボン総量の60パーセント程度がアグリコン化していましたが、宮城県産業技術
総合センターとの共同研究により、約20パーセント高めることに成功しました。
伝統を守りながらもこうした新しい技術開発に取り組むなど、多様な消費者ニーズを掘り起こし、新しい顧客を開拓しようとしています。
「宮城のみそやさん」でお気に入りを探す
仙台味噌の製造販売を行っている蔵元は、宮城県味噌醤油工業協同組合公式ホームページの「宮城のみそやさん」で地区ごとに紹介されています。ここで紹介されている蔵元から直接ネットショップ等 で購入することができます。また、大手通販サイトでも取扱いがあり、購入可能です。なお、組合のホームページでは、仙台味噌を使った料理レシピも豊富に紹介されています。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」