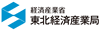【福島県】会津みそ

会津の厳しい気候の中で育まれた赤色辛口米糀みそ。会津料理には欠かすことができない食材のひとつとして地元で愛されています。
登録情報
会津みそ 商標登録第5122652号
権利者
会津味噌協同組合
商品の区分並びに指定商品
第30類:福島県会津地域産のみそ
出願日
2006年4月27日
登録日
2008年3月28日
連絡先
会津味噌協同組合(事務局:合名会社高砂屋商店内)
住所:福島県河沼郡会津坂下町字古市乙141
電話:0242-83-2032
商品の紹介
味噌づくりが盛んな土地
奈良時代以前より東北の経済・文化の中心として栄えていた会津地方は、戦国時代からその時代の有力大名が勢力を競い、
江戸時代になると徳川幕府の二代将軍秀忠の四男である保科正之(会津松平家)が当地を治めることになります。
その正之が江戸初期に編纂した「会津風土記」(1685年)に城内で味噌が作られている記録があり、それが会津における産業としての
味噌づくりと考えられていますので、300年以上の歴史を有する味噌であるといえます。名君であった保科正之のもとで城下も安定し、
様々な家業が生まれるようになった中で味噌づくりも定着し、幕末のころになると味噌づくりが盛んな土地となりました。
会津の質実剛健な気風を感じる味噌
城下町として発展してきた会津ですが、その歴史的な背景が郷土料理に影響を与えてきました。会津藩の質実剛健の気風は華美ではありませんが、
田舎風の中にも凛としたものを感じさせるともいわれます。
冬の長い会津では、味噌は貴重なタンパク源になるため、味噌を使った郷土料理がたくさんあります。サトイモ、モチなどを串に刺して、
甘味噌を付けて囲炉裏端焼く「焼き田楽」は代表的な郷土料理です。他にも「会津みしらず柿の味噌漬」、「味噌納豆」、「鉄火味噌」
(大豆を味噌で炒める保存食)など様々な味噌料理があり、現在でも地元の郷土料理店などで食べることが可能です。
こうした手間と時間をかけて作る「おふくろの味」である会津の郷土料理は、魅力あるスローフードとして訪れる人々の心を捉えています。
「会津みそ」ブランド化の軌跡
会津みそのブランド化の歴史は古く、昭和37年に14社が参加し「会津味噌醸友会」において、会津みそとしての統一した仕込みの実施、
統一した袋の製作、物産展への参加、看板の設置などを展開したことが始まりです。昭和43年には、「会津みそ」の共同製造販売を計画、
チャレンジしたこともありましたが、醸友会が親睦団体的な側面が強くなっていたことから、その後再度後継者たちに呼びかけ「会津醸造倶楽部」を
発足させ、これが中心となって看板の設置・会津産大豆の協同仕入など、会津における味噌業界活動をけん引して活動してきました。
平成18年に地域団体商標の制度が始まり、その申請要件が「法人格を持った業界団体」と規定されたことを期に、任意団体であった会津醸造倶楽部を
「会津味噌協同組合」に改組し、地域団体商標を出願、登録されました。現在、組合ではブランド管理を中心として、「会津みそ」の普及拡大に力を入れています。
「みそ蔵」を訪ねて是非会津へ
「会津みそ」は、会津味噌協同組合の組合店で直接買い求めることが出来るほか、一部の店ではネット販売にも対応しています。また、味噌だけではなく醤油、 めんつゆ、みそ漬け、麹、ごはんのお供等を販売しているみそ蔵もありますので、自分のお気に入りの味を探してみるのも面白いかもしれません。 それらのリストは会津みそ協同組合のホームページで公開されています。協同組合では全国の味噌愛好者に向けて「会津みそ」の魅力を日夜発信しています。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」