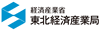【福島県】大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)

地元では原発事故からの避難により作陶できなくなりましたが、一部の窯元は各地で窯の再建をしています。
登録情報
大堀相馬焼 商標登録第5295759号
権利者
大堀相馬焼協同組合
商品の区分並びに指定商品
21類:福島県双葉郡浪江町大堀地域に由来する伝統的な技術・技法により福島県双葉郡浪江町及びその周辺地域で生産された陶磁器製の 急須・皿・徳利・茶碗・湯呑・碗・壷・花瓶・コーヒーカップなど
出願日
2009年3月19日
登録日
2010年1月22日
連絡先
大堀相馬焼協同組合
住所:二本松市小沢字原115-25
電話:0243-24-8812
※二本松市に開設していた仮設工房・販売所・事務所は2019年3月末をもって閉所しました。2019年4月現在、浪江町内での拠点再開を目指して準備中です。
最新情報は組合ホームページを御確認ください。
大堀相馬焼協同組合ホームページ
商品の紹介
大堀相馬焼の魅力
大堀相馬焼は、浪江町の大堀一帯で生産される焼物の総称です。旧藩政時代には「相馬焼」と呼ばれていましたが、国の伝統的工芸品指定を受けてからは、産地である 「大堀」の名を入れた「大堀相馬焼」と呼ばれています。350年以上の歴史があり、相馬藩士であった半谷休閑の下僕、左馬という人によって創始されました。相馬藩は、 この焼物に資金援助や原材料の確保など、保護育成に努めたため、農家の副業として近隣の村にも普及しました。幕末には窯元も100戸を超え、販路も北海道から関東一円、 信州越後方面まで広がり、産地として発展を遂げました。 明治以降は、藩の支援が無くなったことなどの理由から一時期衰退しましたが、戦後復活し、今日、市場は海外まで広がっています。湯呑、酒器、コーヒーカップ、花瓶など 日常使用に適するものがお手頃な価格で購入できるのが大堀相馬焼の魅力です。
国の伝統的工芸品に指定
大堀相馬焼は昭和53年には国の伝統的工芸品に指定されました。福島浜通りの豊かな風土により育まれ、その素朴な味わいの中にもぬくもりと親しみのこもったやさしさが
感じられ、とても強い個性をもっている焼物です。
その大きな特徴は「青ひび」「走り駒」「二重焼」と3つあります。「青ひび」は貫入音(素材と釉薬との収縮率の違いから、焼いたときの陶器の表面に繊細な音を伴って細かい
亀裂が入る)と共に「青ひび」といわれるひび割れが、器全体に広がって地模様になっています。「走り駒」は狩野派の筆法といわれる「走り駒」の絵で、相馬藩の御神馬を
熟練された筆使いで手書きされています。「二重焼」は二重構造になっているため湯が冷めにくく、また熱い湯を入れても持つことができるものです。
「大堀相馬焼」ブランド化の軌跡
大堀相馬焼は平成22年に地域団体商標を取得しましたが、それには、海外で日本の工芸品の商標が押さえられるという報道があり、ブランドを守るために制度を活用した
という背景があります。
その後、伝統を生かし、現代の生活様式や感性に合わせた商品開発及びブランド開発を行うことで販路を広げてきました。近年は、インターネット上での販売にも積極的に
取り組んでいます
また、海外の方がより値段がつくということで、上海、パリ、サンフランシスコ、ハワイなど海外の展示会へ出展し、販売を広げている意欲的な窯元も現れています。
海外で日本の工芸品に注目が集まる中、海外でのPR活動のメリットは大きいものがあり、今後さらに期待されています。
窯元の復興を目指して
平成23年に発発生した原発事故により浪江町民は避難を余儀なくされ、地元での作陶ができなくなるという試練が訪れました。しかし翌年、二本松市の協力を得て、
二本松市小沢工業団地に「陶芸の杜 おおぼり二本松工房」が完成。展示室・事務室・会議室・陶芸教室・ろくろ場・釉薬かけ物置・仮眠室・窯場などを備えた床面積
約720平方メートルの仮設の工房が作られ、新しいスタートを切ることができました。従来どおり陶芸教室(要予約)も開催されており、コーヒーカップや湯呑みづくりを
体験することができます。
工房の再開は、大堀相馬焼の維持・継承と離散した窯元、浪江町民をつなぐ拠点となり、ふるさとを想う「憩いの場」の役割も果たしています。現在は9軒の窯元が福島県内
各地で新しい環境の下、伝統を守りながら作陶に向き合い、誰からも親しまれる製品づくりに日々努力しています。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」