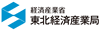【秋田県】川連漆器 (かわつらしっき)

武具づくりで培われた漆塗りの技術が漆器産業として発展しました。今でも伝統を守る熟練の職人が一つ一つ丁寧に作り上げています。
登録情報
川連漆器 商標登録第5141290号
権利者
秋田県漆器工業協同組合
商品の区分並びに指定商品
21類:秋田県湯沢市川連町・旧稲川町駒形地区及び三梨地区に由来する製法により秋田県湯沢市川連町・旧稲川町駒形地区及び 三梨地区で漆塗りを施した杯・皿・重箱・鉢・べんとう箱・椀・片口・茶托・茶筒・茶櫃・なつめ・菓子器・盆・膳・箸・箸箱・しゃもじ・急須台・おしぼり置き・花器
出願日
2007年9月12日
登録日
2008年6月13日
連絡先
秋田県漆器工業協同組合
住所:湯沢市川連町字大舘中野142番地1
電話:0183-42-2410
商品の紹介
武士の副収入を得る方法
川連漆器は今から800年前、武士の内職として武具の漆塗りから始まったといわれています。源頼朝の家臣でこの地を治めた小野寺重道の弟・道矩が、武士に副収入を得る方法として教えたようです。
最も技術が高く漆本来の美しい光沢が映える「花塗り」で作られた箸から家具までの幅広いアイテムは、熟練の高い技術を持つ職人が一つ一つ真心を込め作り上げています。
武具の漆塗りが発祥
漆塗りが本格的に漆産業として始まったのは17世紀中頃からで、もとは武具の漆塗りが発祥といわれます。文化12年(1815年)には、漆器の販路を他に開く許可が藩から下り、広く普及していきました。 こうして、藩の保護政策のもとで椀、膳、重箱など幅広い漆器がつくられるようになり、沈金、蒔絵などの飾りも加わって、産業基盤が大きくなりました。漆器の主流はお椀で、生産量の6割以上を 占めていますが、現在では様々なアイテムが幅広く開発されています。
「堅牢な下地」「花塗り」「沈金技術」で作られた実用漆器
「川連漆器」は何回も繰り返される「地塗り」と「中塗り」を経て、塗り立てと言われる「花塗り」で仕上げて乾燥するのが特徴です。原材料の樹種は栃、桂が主ですが、重箱などは朴の木を使うのが
一般的です。
漆器としての特徴はまず、堅牢な下地を持っていることです。そのため木地に直接生漆を塗る「地塗り」を行います。
二つ目の特徴は、上塗りは塗り立てともいわれる「花塗り」です。これは、ムラなく平滑に漆を塗る技術ですが、埃をつけないように大変に気をつかう作業です。
三つ目は沈金技術です。蒔絵よりも歴史は新しく、明治からといわれています。手前に引く沈金かんなを開発し、これにより浅彫りを可能にし、繊細で立体感のある沈金ができるようになりました。
このようにできた漆器は、丈夫で使いやすく廉価なため、実用漆器として愛されています。
「川連漆器」ブランド化の軌跡
「川連漆器」は、昭和51年に国の伝統的工芸品、平成8年には県の伝統的工芸品にも指定され、平成10年、平成12年の県の全国漆器展では内閣総理大臣賞を受賞しました。
こうした栄誉に輝く中、海外産の漆器が出回るようになったため、差別化を図るため地域団体商標の取得を目指しました。同時に、商標登録により生産者の創作意欲の向上と伝統を守るという気概が醸成されました。
毎年地元で開催される「蔵出し市」(8月開催)、「川連塗りフェア」(10月第3金、土、日、月曜日開催)等展示販売会は、愛好者に人気を博しています。また、展示会を通したPRや物産展などへ積極的な参加を通して
「川連漆器」の魅力を伝え、産業振興に努めています。近年は若手グループや外国デザイナーとのコラボによって、新しい感性を取り入れた新商品開発にも取り組んでいます。
また、平成24年度には、震災復興の関連企画として、川連漆器の硯箱、宮城県石巻市の雄勝硯、福島県双葉郡の大堀相馬焼とのコラボレーションにより硯箱一式を製品化するという取組も実施しました。
伝統工芸館で漆器作りを体験
平成21年に「川連漆器」の拠点施設として、「湯沢市川連漆器伝統工芸館」がオープンしました。館内には約800点が並ぶ展示販売フロアがあり、実物を見て触れて選ぶことができます。 質と量は県内随一の品揃えです。2階には資料館があり、職人技の歴史を学べるほか、椀師工程絵図や湯沢市の名所、史跡、物産が大パネルに蒔絵、沈金で描かれ、川連漆器を存分に堪能していただけます。 予約すれば沈金と蒔絵の体験もできますので、参加してみてはいかがでしょう。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」