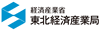【山形県】山形佛壇

江戸から仏壇の製造技術を持ち帰り、製造工程を分業制にするという画期的な方法によって発展させました。その芸術性は高く評価されています。
登録情報
山形佛壇 商標登録第5055867号
権利者
山形県仏壇商工業協同組合
商品の区分並びに指定商品
第20類:山形県山形市及び天童市で生産された仏壇
出願日
2006年8月16日
登録日
2007年6月22日
連絡先
山形県仏壇商工業協同組合
住所:山形市松見町8番11号
電話:023-632-1516
商品の紹介
木のぬくもりを感じさせる芸術品
仏壇の製造は、江戸時代の中期、享保年間(1724年から1777年)に、星野吉兵衛によって始められました。吉兵衛は江戸浅草の工匠に弟子入りし、木彫りを学び山形へ帰り、欄間、仏具等の彫刻の技を 伝えました。昭和55年には、最も北にある仏団産地として国の伝統的工芸品に指定され、その堅牢で荘厳な独自なデザインの中にも木のぬくもりを感じさせる芸術品です。現在は、山形市、天童市、尾花沢市、 酒田市が代表的な産地として知られています。
江戸浅草で学んだ技術が根付く
江戸から仏壇製造技術を持ち帰った星野吉兵衛の息子が、その後家業を継ぎ、父同様に江戸で彫刻を学びました。彼は、古くからある漆塗師、蒔絵師、金工錺(きんこうかざり)職人などを統合し、
チームで仏壇を組み立てるという画期的なアイデアを考え出し、製作販売を始めました。
現在のような分業制になったのは明治28年頃といわれていますが、木地、宮殿彫刻、金具、塗、蒔絵、箔押し、仕組みの七分業に分かれて量産されるようになり、東北6県のみならず、北海道にも
販売ルートを拡大し、確固たる地域を気づいてゆきました。
分業体制で組み立てられる佛壇
伝統的な金仏壇は明治以来、七工程に分かれて分業体制で一貫して製造されています。
釘を使わず、木の凹凸を合わせる「ほぞ組み」による組立て。柔らかいシナの木に欄間や柱につける細やかで奥行きのある彫刻。真ちゅう板に何百種類ものたがねを使い分けならが模様を付ける錺金具作り。
木目が見えるよう漆を塗っては研ぐ工程を何度も繰り返す「木目出し」。そして漆の上に描く最高級の「盛り上げ蒔絵」。細かなパーツから宮殿や彫刻を仕上げ、最後に全体を組み立てて作り上げ、完成と
なります。
こうしたそれぞれ専門の職人による製造方法が「山形佛壇」を特徴づけているものです。
「山形佛壇」ブランド化の軌跡
伝統芸術を受け継ぐ山形佛壇ですが、それだけに過去には偽物が出回ることもありました。その対策の一環として、中小企業中央会からの勧めにより地域団体商標を出願し、平成19年に登録されました。
これにより偽物も排除され、生産者の間にブランドの品質を守る気概が生まれました。
現在、新しい挑戦として、ライフスタイルや住宅様式の変化に対応した和室・洋室どちらにも合う仏壇づくりを目的とした意匠開発に取り組んでいます。平成26年度からは、山形県産材(金山杉等)を使った
仏壇制作へのチャレンジとして原材料対策にも取り組んでいます。また、中国やベトナムからの安価な輸入仏壇が大量に国内に出回る中、「山形佛壇」のブランドを掲げて、新規の需要開拓を行うべく展示会に
積極的に参加するなど、組合をあげて産地の発展に励んでいます。
お手頃価格もある山形仏壇
県内の主要仏壇仏具店のほか、全国の仏壇仏具店などに取扱いがあります。製造工程の検査基準ごとに価格レベルも三段階用意されており、こだわりの職人技で製造した最高級の仏壇から、 購入しやすい低価格の仏壇まで、バラエティに富んでいます。最近はライフスタイルに合わせたカジュアルタイプの仏壇も人気です。仏壇は宗派による形の違いもあるため、購入の際には 店の人に相談して確認いただくことをお勧めします。
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」