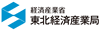【山形県】米沢織

米沢藩主・上杉鷹山が織物の先進地であった新潟の小千谷から技術を導入、産業として発展させました。
登録情報
米沢織 第5026436号
商品の区分並びに指定商品
第24類:山形県米沢市内産の織物
権利者
米沢織物工業組合
出願日
2006年4月1日
登録日
2007年2月16日
連絡先
米沢織物工業組合
住所:米沢市門東町1丁目1番87号
電話:0238-23-3525
米沢織物工業組合(米沢繊維協議会ホームページ)商品の紹介
江戸時代後期には一大絹織物産地に
米沢織の歴史は、江戸時代、米沢藩九代藩主の上杉鷹山が、藩財政を建て直すための藩政改革の一環として、藩士の婦女子に青苧(あおそ)の 縮織を習得させたことに遡ります。当時、織物の先進地だった新潟県の小千谷から技術者を招き、縮み役場を寺町蔵屋敷内に設けて指導にあたらせました。 その後、領内で養蚕から織までを行う絹織物産地に転換。紅花や紫紺などの植物染料を使った染色織物が確立し、江戸時代後期には一大絹織物産地となりました。 明治以降は時代の変遷とともに化学繊維品も発達し、現在では総合的な織物産地として知られています。
多品種・少量、産地内での一貫性産体制
米沢織は、糸の製造から染色、織り上がって仕上げが施され、美しい呉服地・服地が出来上がるまでには多くの工程があります。
さらに、ニットや縫製などを含め、関連業種が連携を保った産地内での一貫生産体制がとられています。どれ一つ賭けても優れた
織物はできないため、各工程ではそれぞれの役割に最高の技術と情熱をかけて取り組んでいます。
洋装部門では、女性向けのスーツやワンピース、コート、フォーマルドレスの高級生地を作っていて、デザイナーズブランドや有名
ブランドでも使用されています。また、ヨーロッパ、アメリカ、中国などアジア向けの輸出織物も生産しています。
和装部門では、婦人ものの着物(紬、訪問着、つけ下げなど)や帯、雨コート、男物の着物や袴、帯、長襦袢などを作っています。
このように、多品種・少量生産の体制がとられ、非常にバラエティに富んでおり、単なる織物産地としてだけでなく「小さくともキラリと光る産地」
「オンリーワン産地」を目指しています。
「米沢織」ブランド化の軌跡
米沢織は高品質な織物のブランドとしては知られていました。特に合成繊維開発分野では、いち早く婦人服地の分野で技術開発をしてきたため、
織の分野ではイタリアのコモに匹敵する世界一の技術力を誇っていたのです。この高い技術力により、近年は、ノーベル賞授賞式の晩餐会会場など、
公式行事で掲げられるスウェーデン王立工科大の旗の復元を手がけています。
そうした中、地域団体商標の制度を利用して、生地のみならず、製品を通じてブランド化を図ることにしました(平成19年登録)。
これには、海外輸出を視野に入れ、アパレル企業も巻き込むという戦略がありました。
東日本大震災後は、東北復興の流れの中で、米沢織を使うことで商品の差別化を図りたいというアパレル企業側の思惑もあり、ニーズも増えています。
また、地方創生に向けて高付加価値化、ブランド化を進めるため、デザイナーと組んで新商品を開発する「Yonezawa Textile Project」を若手経営者有志、
山形大学などと連携して進めています。中には、米沢織の伝統生地をアクリル樹脂で固め、有機EL照明でライトアップしてオーロラのように見せるオブジェや
富裕層向けの部屋着が試作されています。
米沢織りに触れ、学ぶ
米沢市内には、米沢織物歴史資料館に組合が運営する産直ショップ「おりじん」があります。また、市内の上杉御廟所前に、米沢織と 紅花染めが体験できる「染織工房わくわく館」があり、実際に米沢織に触れ、学ぶことができます。ここには30坪ほどの広いギャラリーが あり、米沢織の着物、袴、帯などが常時展示され、販売もしています。気軽に購入できるオリジナル商品や個性的なセレクト商品も 多数取りそろえていますので、是非御利用ください。
産直ショップ「おりじん」の詳細は、米沢繊維協議会ホームページで御確認ください。
米沢繊維協議会ホームページ
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」