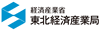【青森県】大鰐温泉もやし

津軽藩主にも献上していたという逸話が残る冬野菜。一子相伝で栽培技術が受け継がれてきました。
登録情報
大鰐温泉もやし 商標登録第5499485号
権利者
プロジェクトおおわに事業協同組合
商品の区分並びに指定商品
31類:青森県南津軽郡大鰐町の大鰐温泉水を利用し、同町に由来する製法により、同町で生産されたもやし
出願日
2011年6月8日
登録日
2012年6月8日
連絡先
プロジェクトおおわに事業協同組合(事務局:大鰐町地域交流センター鰐come内)
住所:青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字長峰字下川原9-92
電話:0172-49-1126
商品の紹介
江戸時代から名の通った温泉
湯量の豊富なことで有名な大鰐温泉ですが、その発見は建久年間(1190年代)まで遡ります。歴代の津軽藩主の湯治場として江戸時代から名の通った温泉でした。 ここでは、農家が代々受け継いだ小八豆という在来種の大豆でもやしを作り、当時で訪れた津軽藩主に献上していました。
冬場の貴重な栄養源だったもやし
350年以上の歴史があるその栽培技術は一切口外されず、一子相伝で受け継がれてきました。特に冬が長く厳しい津軽地方にとって、温泉熱を利用して冬期に栽培出来た冬野菜のもやしは 貴重な野菜、重要な栄養源でした。しかし、時代の流れとともに、収穫作業の過酷さや鮮度維持の難しさ、流通面など様々な問題から生産者は減少しています。このため町では、伝統技術の 継承などを目的とした事業を推進しています。
秘伝の技術で高品質なもやしづくり
大鰐温泉もやしは、独特の芳香、味、品質の高さが評価されていますが、中でも特徴的なのはシャキシャキとした歯触りで、一般的な水耕栽培ではないことがこの歯触りを生みます。
その栽培方法は代々受け継がれてきた秘伝技術そのままです。無化学肥料、無農薬、昔ながらの土耕栽培で、温泉熱で地温を高めて栽培。もやしの品質は、播種4日後の成長度合いで決まるため、
温泉熱による温度調整には熟練を要し、温泉が流れる配管の深さや配置、湯量などに関する技術はトップシークレットです。さらに、仕上げまで温泉を使用し水道水は使いません。湯温の調整なども
個々に伝わる伝統技となっています。
作業は11月から4月頃まで、毎日早朝2、3時から昼過ぎまで10時間程行われ、各農家につき一日約40キログラム(120束)程度が出荷されます。
「大鰐温泉もやし」ブランド化の軌跡
平成21年に「プロジェクトおおわに事業協同組合」を設立し、温泉交流施設「大鰐町地域交流センター 鰐come(ワニカム)」を活用した売り込みをはじめ、東京の有名百貨店や青森県出身の料理人、
マスコミやフードジャーナリストなどに地道にPRしてきました。また時には生産者が東京に行き、消費地でのもやしの価値を直接見ることで生産者自身の意識改革も行いました。こうしてコツコツと
ブランド化に取り組む中で、平成24年には地域団体商標にも登録されました。
現在、地域を代表するブランド食材として、さらに地域振興にいかして行きたいという動きが活発化しています。生産が間に合わないほど人気が出るようになり、増産が目下の課題ですが、
地域団体商標登録に伴う取組の推進や青森県のアンテナショップ「あおもり北彩館」等とともに、少量多品種の発送事業なども準備中です。
「幻のもやし」を地元で味わってみてください
平成28年11月に開催された「大鰐温泉もやしフェスタ」では、もやしの販売と料理が提供されましたが、瞬く間に完売しました。現在、生産が足りない程の人気を博しているため、
現地でも入手困難と言われている状況ですが、町内には「大鰐町地域交流センター 鰐come(ワニカム)」ほか、2店でもやしと加工品の取扱いがあります(入荷状況次第のため要確認)。
また、町内には「大鰐温泉もやしラーメン」を提供している老舗食堂も数軒あります。詳しくはプロジェクト大鰐事業協同組合のホームページを御覧ください。
是非大鰐町を訪れ、「大鰐温泉もやし」を御賞味ください。
プロジェクトおおわに事業協同組合運営「鰐come」ホームページ
文章引用:2017年2月発行 東北経済産業局知的財産室編「きらり!TOHOKU 地域ブランドコレクション」
農林水産省「地理的表示(GI)」登録情報
大鰐温泉もやしは、地域団体商標のほかに、農林水産省の「地理的表示(GI)」にも登録されています。
特定農林水産物等の名称
大鰐温泉もやし(オオワニオンセンモヤシ)、Owanionsen Moyashi
権利者
大鰐温泉もやし増産推進委員会
特定農林水産物等の区分
第1類 農産物類 野菜類(もやし)
登録日及び登録番号
2020年3月30日 第90号
その他
特性等の詳細情報は、農林水産省のホームページを御覧ください。