
福島県
奥会津編み組細工
産 地
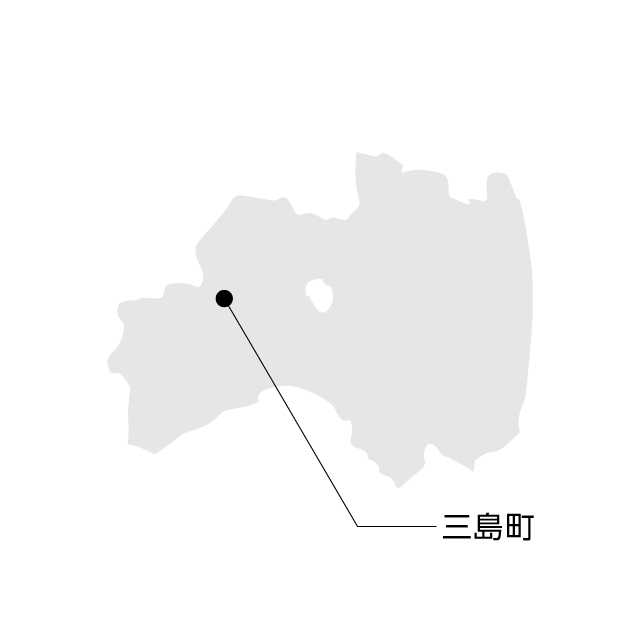
指定年月日
平成15年9月10日
歴史
奥会津地方は、全国でも有数の豪雪地帯であり、雪国特有の生活文化が育まれてきました。奥会津編み組細工も雪国だからこそ継承されてきたものです。
その原形は、会津農書写本(1748年著)や東遊雑記(1788年著)、伊南伊北谷四ヶ組風俗帳(1807年著)に記録されており、元来農作業や山仕事、日常の生活に用いる籠や笊として作られてきたものです。
雪に閉ざされる冬の間の仕事として、親から子へ、子から孫へと受け継がれ、素朴で堅牢な工芸品へと発展してきました。
その過程には、三島町が進めてきた生活工芸運動が大きく影響しています。昭和47年から町主催の展示会を行うなどの支援を続けてきたことで、地域住民に浸透してきました。
現在では100人を超える工人たちが取り組み、地域の文化と経済の一端を担っています。
特徴
奥会津編み組細工には、ヒロロ細工・山ブドウ細工・マタタビ細工の3種類があります。
ヒロロ細工は、ヒロロ(和名:ミヤマカンスゲ)を主な材料とし、手さげ籠等の製品が作られています。編み目が細かく、レース編みのような仕上がりが特徴で素朴さの中にも独自の繊細さがあります。
山ブドウ細工は、強靭な山ブドウ蔓の皮を材料とし、手さげ籠等の製品が作られています。山ブドウの皮は使い込むほどにつやが出て素朴な魅力を増します。
マタタビ細工は、マタタビ蔓を材料とし、米研ぎ笊、四つ目笊等主に炊事用具として用いられてきました。水切れが良いことに加え、水分を含むとしなやかになり手触りがよいのが特徴です。
3種とも材料の採取から完成に至るまで全て手作業で行われています。今では手提げ籠などいろいろな工芸品の材料として使用されています。
産地PR・最近の取り組み、課題など
通年で行っている生活工芸館での展示販売のほか、地元において年2回の展示販売イベントを主催しています。会津管内や全国より集まった編み組細工を展示・販売いたします。全国で最も編組品の集まる機会と自負しておりますので、ぜひ、三島町へお越しください。材料採取や制作のようすなどはHPやSNSでの広報活動も行っておりますのでご覧ください。
高齢化により編み組細工従事者が減少傾向にありますが、新たな後継者の育成を図る為、教室を開催し、伝統工芸士による技術技法の指導を行っています。また、山ブドウ蔓など原材料の減少・高齢化によって確保が困難な材料については、採取地の情報提供のお願いや委託採取により、安定した確保・提供を行うため活動しています。
産地イベント
◇6月 ふるさと会津工人まつり(町主催)
◇10月 会津の編み組工芸品展
◇3月 全国編み組工芸品展
製法や工程について
製造工程

- 材料採取
- 根ほぐし
- 乾燥
- 縄綯い
- 底編み(技法:矢羽根編(やばねあみ)、棚編(たなあみ))
- 立ち上げ編み(技法:矢羽根編(やばねあみ)、棚編(たなあみ))
- 縁編み・縁どめ
- 紐付け

- 材料採取
- 乾燥
- 浸水
- 鞣(なめ)し
- 幅揃(はばそろ)え
- 底編み(技法:二本飛網代編(にほんとびあじろあみ)、笊編(ざるあみ)、四(よ)つ目(め)編(あみ))
- 立ち上げ編み(技法:二本飛網代編(にほんとびあじろあみ)、笊編(ざるあみ))
- 縁巻き(技法:矢筈(やはず)巻縁(まきふち))
- 紐付け
- 仕上げ磨き

- 材料採取
- 皮(かわ)剥(は)ぎ
- 割(さ)き
- 扱(こ)き
- 幅揃(はばそろ)え
- 底編み(技法:二本飛網代編(にほんとびあじろあみ)、四(よ)つ目(め)編(あみ))
- 立ち上げ編み(技法:笊編(ざるあみ)、二本飛網代編(にほんとびあじろあみ))
- 縁巻き
- 晒し(技法:寒晒(かんざらし)、雪晒(ゆきざらし))
技術・技法
- 「ヒロロ細工」にあっては、次の技術又は技法によること。
- ヒロロ縄の太さは2ミリメートルから4ミリメートルとし、10センチメートルの長さに縒りが20回以上あること。
- 底編み及び立ち上げ編みは、「矢羽根編」又は「棚編」によること。
- 「山ブドウ細工」にあっては、次の技術又は技法によること。
- ヤマブドウの皮は、鞣しを十分に行い、繊維に沿って切断し、幅の調整を行うこと。
- 手さげ籠類の底編み及び立ち上げ編みは、「二本飛び網代編」又は「笊編」によること。
- 手さげ籠類の縁巻きは、「矢筈巻縁」によること。
- 角箱籠類の底編みは、「四つ目編」又は「二本飛び網代編」によること。立ち上げ編みは、「笊編」によること。
- 丸籠類の底編みは、「笊編」「四つ目編」又は「二本飛び網代編」によること。立ち上げ編みは、「笊編」又は「二本飛び網代編」によること。
- 「マタタビ細工」にあっては、次の技術又は技法によること。
- 材料の下ごしらえは、皮剥ぎ、割き、扱き、幅揃えを行うこと。
- 米研ぎ笊の底編みは、二本の材料を一組とする「二本飛び網代編」で編み、一本の材料で「二本飛び網代編」により底を丸くすること。立ち上げ編みは、「笊編」によること。
- 小豆漉し及び蕎麦笊の底編みは、二本の材料を一組とする「二本飛び網代編」によること。立ち上げ編みは、一本の材料で「二本飛び網代編」によること。
- 四つ目笊の底編みは、二本の材料を一組とする「四つ目編」によること。立ち上げ編みは、「笊編」によること。
- 籠類の底編みは、二本の材料を一組とする「笊編」によること。立ち上げ編みは、一本の材料で「笊編」によること。
- 製作後は、「寒晒」又は「雪晒」を行うこと。
原材料
- 「ヒロロ細工」にあっては、奥会津の山間部で採取されたミヤマカンスゲ(別称 ホンヒロロ)、オクノカンスゲ(別称 ウバヒロロ)とすること。
- 「山ブドウ細工」にあっては、奥会津の山間部で採取されたヤマブドウの皮で、二枚皮になる前の一枚皮とすること。
- 「マタタビ細工」にあっては、奥会津の山間部で採取された若年の成熟したマタタビの蔓とすること。縁の芯の材料はクマゴヅル又は同等の材質を有するものとすること。
産地組合の概要
- 組合名奥会津三島編組品振興協議会
- 所在地〒969-7402 福島県大沼郡三島町名入字諏訪ノ上395 三島町生活工芸館内
- TEL0241-48-5502
- FAX0241-52-2175
- ホームページhttps://www.okuaizu-amikumi.jp/
- e-mailkougeikan@town.mishima.fukushima.jp
- 企業数 -
- 従事者数124名
- 年間生産額約3千万円
- 伝統工芸士7名
- 主な製品(ヒロロ細工)手提げ籠・ショルダー・抱えバック・巾着等
(マタタビ細工)米とぎ笊・四つ目笊・そば笊・手提げ籠等
(山ブドウ細工)手提げ籠・ショルダー・抱えバック・おにぎり入れ等
