
山形県
山形鋳物
産 地
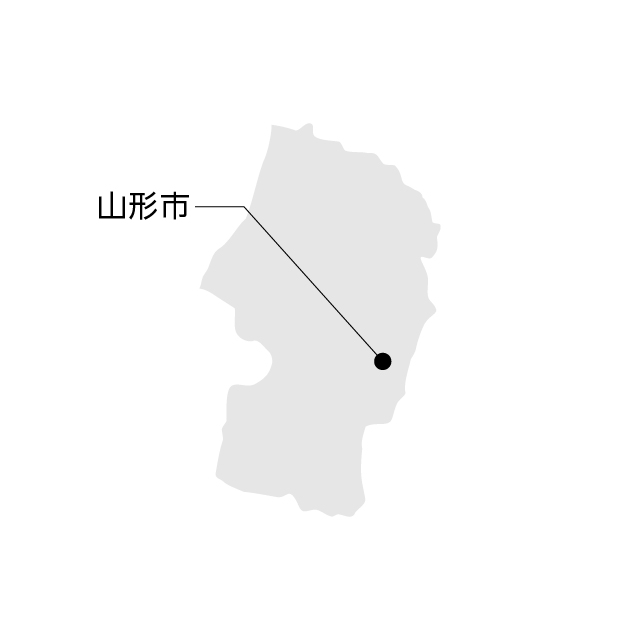
指定年月日
昭和50年2月17日
歴史
およそ900年前、平安時代の康平年間に、乱平定のため源頼義が山形地方を転戦し、その時従軍した鋳物師が山形市内を流れる川の砂と付近の土質が鋳物に最適であることを発見、何人かが留まり、これが山形鋳物の始まりと言われております。
12代目の最上義光が、慶長年間ご城下の再編成を行い火を扱う町づくりをしたのが、鋳物産地としての基礎をつくり日本における工業団地の始まりとも言われております。
元和元年(1615年)、京都などの先進地を視察し山形ブロンズ鋳物の技術が確立され、その後数十年で梵鐘や灯籠など製作されるまで、飛躍的に発展しました。
特徴
山形鋳物は機械鋳物と工芸鋳物に大別されますが、工芸鋳物は鉄製のものと銅合金(ブロンズ)のものとがあります。
伝統に磨かれた独特の鋳型作り、文様押し、肌打ち、漆仕上げ等伝統的技法により薄物で繊細な肌と形の正確さが特徴です。
産地PR・最近の取り組み、課題など
伝統的な技術、技法、原材料の特質を生かすことを基本理念とすることは言うまでもありません。しかも現代生活にマッチしたものは何であるかを前提とし、現代生活にマッチした製品は何かを常に希求し、産地振興の真のものは何であるか、どう対策を打ち出すべきか、必死で検討思考して新しい発想を展開することが、今後産地として課せられた何にも増しての急務であります。
これをモットーに製品開発を行い、各地の伝統的工芸品展へ出展しています。
製法や工程について
製造工程





技術・技法
- 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
- 砂型であること。
- 溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。
- 鋳型の造形は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。
- 「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。
- 鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
- 鉄器にあってはその表面に漆及び鉄しょうを用いて着色をし、銅器にあってはその表面に硫酸銅、ろくしょう又は鉄しょうを用いて着色をすること。
- 鉄器のうち料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。

原材料
- 鋳物の素材は、鉄器にあっては砂鉄又は鋳物用銑鉄とし、銅器にあっては銅合金とすること。
- 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
産地組合の概要
- 組合名山形鋳物伝統工芸組合
- 所在地〒990-2351 山形県山形市鋳物町22 長文堂 内
- TEL023-643-7141
- FAX023-643-7141
- ホームページhttps://www.chuokai-yamagata.or.jp/imono/
- 企業数24社
- 従事者数60名
- 年間生産額 -
- 伝統工芸士3名
- 主な製品茶の湯釜、鉄瓶、青銅花瓶、置物、鉄鍋、美術工芸、インテリア、エクステリア、その他日用品、工芸美術鋳物全般
