
山形県
天童将棋駒
産 地
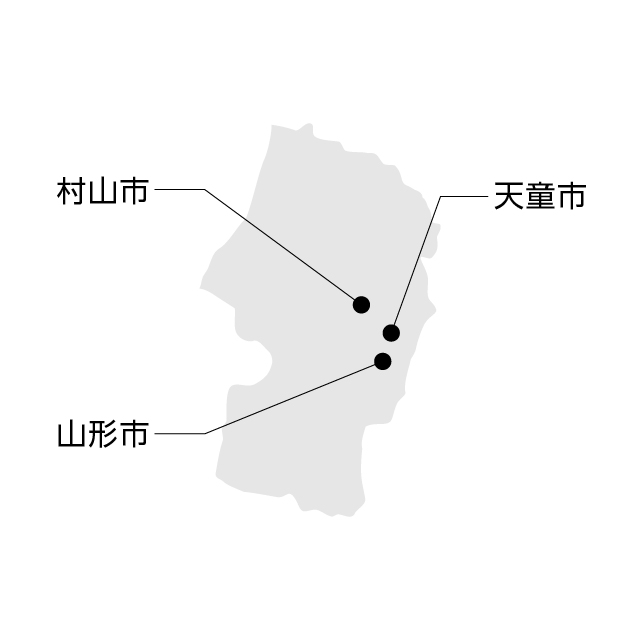
指定年月日
平成8年4月8日
歴史
将棋駒の製造が天童で始まったのは、江戸時代末期までさかのぼります。明和4年(1767年)上野国小幡(現・群馬県甘楽町小幡)から出羽国高畠(現・山形県高畠町)に移封された織田氏は、所領2万石のうち3分の2に近い13,000余石は、天童を中心とする村山地方にありました。天保2年(1831年)に高畠から天童に移館し、さらに嘉永元年(1848年)には、高畠にあった所領も所領交換により村山に集中するようになり、実質、天童織田藩が実現しました。しかしながら、凶作が続いたことにより藩の財政が困窮し、救済策として家臣に将棋駒製作の内職を積極的に奨励しました。「将棋は戦闘を練る競技であるから、武士の面目を傷つける内職ではない」というのがその理由でした。
天童織田藩時代は、木地造りと書きの分業形態で将棋駒を製造していました。主に手工業生産が中心でしたが、明治時代末期から機械化による大量生産が進み昭和初期には、安価で良質な天童将棋駒の供給が可能となりました。しかしながら、昭和40年代に入ると、生産の主体は彫り駒に移り、彫埋、盛上の技術が研究され、製品化されました。現在では、一般財団法人伝統的産業振興協会認定の伝統工芸士が作る盛上駒は、プロ棋士のタイトル戦でも使われています。
特徴
駒木地に使われる主な木材は、薩摩(鹿児島)ツゲや御蔵島(東京都)ツゲなどを使用します。工程は、駒の木地を作る工程と出来た木地に漆を使い蒔絵筆で文字を入れる仕上げ工程に大別されます。
駒文字には楷書体と草書体があり、特に草書体は天童将棋に伝承されている独特で美しい文字です。また、近年は彫埋駒、盛上駒の研究も進み、水無瀬や巻菱湖などの行書体で多く作られています。
産地PR・最近の取り組み、課題など
例年、天童市や首都圏において「天童将棋駒祭り」が開催されています。この駒祭りでは、将棋を指す方だけでなく、初心者や指さない方にも楽しめるような企画も盛り込まれています。
また、天童将棋駒の産地においては、人間将棋等の将棋や将棋駒に関するイベントが開催されています。産地を訪問すれば、店を回りお気に入りの書体の駒を求める楽しみも味わえます。
製法や工程について
製造工程
天童将棋駒に百五十年という時間に培われた知識と、そこから継承され、さらに鍛えられた技術が製作工程の中にいくつも生かされてます。本物が生み出す質感をお確かめください。

木地は丸太材より数種類の特殊な丸鋸を使用して1枚1枚手作業で行います。その熟練した技で、木地の木目を大事にしながら(端切り・側切り・底切り・剣立て)、小割り、仕上げまでの作業を行います。

印刀一本で巧みに文字を掘り込んでいきます。字体の簡略度により、黒彫、並彫、中彫、上彫、銘駒などの種類があります。さらに下地漆で文字を埋め込み、瀬戸みがき等を使って平滑等に仕上げたものが彫り埋め駒となります。

工程彫り埋め駒に蒔絵筆を使い、文字を漆で浮き立たせ、乾燥のあと丁寧に研きあげたものです。技術的に難しく、将棋駒の中で最高級品です。

書き駒は、筆を使い漆で木地に文字を直接書いたものです。草書体と楷書体があります。天童将棋駒といえば書き駒の草書体と言われるほど伝統があります。
技術・技法
- 将棋駒の木地作りにあっては、玉切りした材を、大割り、小割り及び駒切りをすること。
- 書き駒にあっては、駒木地に筆を使用し、漆を用いて、将棋駒独特の書体により、直接書くこと。
- 彫り駒にあっては、字形から字母紙に陰影を写し取り、陰影を取った字母紙を切り取り、駒木地にのりで張り付け、印刀で彫り、目止めをしたあと、漆入れ、下地漆入れ、又は漆盛り上げにより仕上げること。
原材料
- 駒木地にあっては、ホオノキ、ハクウンボク、イタヤカエデ、マユミ若しくはツゲ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
- 漆は、天然漆とすること。
産地組合の概要
- 組合名山形県将棋駒協同組合
- 所在地〒994-0013 山形県天童市老野森1-3-28 天童商工会議所内
- TEL023-654-3511
- FAX023-654-7481
- ホームページhttp://www.tendocci.com/koma/
- 企業数20社
- 従事者数56名
- 年間生産額約89百万円
- 伝統工芸士7名
- 主な製品将棋駒、置駒、根付駒等
